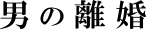「家族法(民法)が変わる」「共同親権が導入される」と聞き、ご自身の生活にどう影響するのか、ご不安やご関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
令和6年5月に改正法が成立し、令和8年4月1日から施行される予定です。
この改正は、私たちの生活、特に離婚後の親子関係に大きく関わる内容を含んでいます。主な改正点を分かりやすく解説します。
1. 離婚後の「共同親権」が選択可能に
これが最大の変更点です。
- 現行法:
離婚後は、父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」しか認められていません。 - 改正法:
離婚時に、父母の話し合いによって「共同親権」を選ぶことが可能になります。もちろん、これまで通り「単独親権」を選ぶこともできます。
もし話し合いで決まらない場合は?
父母間で合意できない場合や、話し合い自体が困難な場合は、家庭裁判所が判断します。
裁判所は、「子の利益(子どもの幸せや健全な成長)」を最も優先し、「共同親権」が適切か、あるいは父母どちらかの「単独親権」が適切かを決定します(改正民法819条第7項)。
【重要】DV・虐待がある場合のルール
改正法では、DVや虐待のおそれがあり、共同親権では「子の利益が害される」と裁判所が判断した場合は、必ず「単独親権」としなければならないと定められています(改正民法819条第7項各号)。
2. 養育費と親子交流(面会交流)について
子どもの健やかな成長のため、養育費の確保や交流に関するルールも強化・整備されます。
養育費の確保(より確実に受け取るために)
- 法定養育費制度の新設:
養育費の取り決めをしないまま離婚した場合でも、法定額の養育費の支払いを請求できる制度が作られます(改正民法766条の3)。 - 強制執行の簡素化:
養育費が支払われない場合の強制執行(給与や預金の差し押さえ)の手続きが、利用しやすく簡素化されます。
親子交流(「面会交流」から名称変更)
- 祖父母等との交流:
子どもと離れて暮らす親だけでなく、祖父母といった「父母以外の親族」も、家庭裁判所が「子の利益のために特に必要がある」と認めた場合には、子どもとの交流(面会)ができるようになります(改正民法766条の2第1項)。 - (補足)交流の強制力について:
一方で、交流の取り決めが守られない(例:会わせてもらえない)場合に、裁判所が交流を強制的に実現させる「直接強制」の導入は、今回は見送られました。取り決めの実効性をどう確保するかは、引き続き課題として残っています。
3. その他の主な改正点
- 財産分与「2分の1ルール」の明文化:
離婚時の財産分与について、裁判実務で定着していた「特別な事情がない限り、夫婦で築いた財産は2分の1ずつ分ける」というルールが、法律の条文として明確に記載されました(改正民法768条第3項)。 - 離婚原因の見直し:
法律上の離婚原因の一つであった「強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」という規定が削除されました。
まとめ
これらの改正は、家族のあり方が多様化する現代社会に合わせて、「子の利益」を第一に守ることを目指したものです。
施行に向けて、今後公表される最新情報に注目していく必要があります。