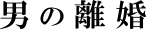夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚後の親権者をどちらかに決めなければ、離婚をすることはできません(離婚後の単独親権)。
親権者を決めるにあたっては、まずは夫婦間で話し合い、話し合いで決められなければ、裁判で決めることになります。
夫婦間の話し合いで決める場合には、親権者の決め方について、特に決まったルールはありません。夫婦の意見が合致すればOKです。
話し合いで決まらない場合、裁判所は何を基準に判断する?
問題は、夫婦間で話し合いがつかず、裁判で決める場合です。裁判所は、どのような基準で親権者を決めるのでしょうか。
たとえば、あなたなら、見知らぬ人から、「僕と妻と、どちらが子どもの親権者にふさわしいか決めてくれないか」と頼まれた場合、どのように親権者を決めますか?
親権者になりたい気持ちが強い方?経済力がある方?子どもが一緒に住みたいと言った方?家事がきちんとできる方?
…なかなか難しい問題です。
裁判所が最も重視するのは「これまでの子育て実績」
このとても難しい問題の解決に当たって、最近の裁判所が重視する判断要素は、「これまで、どちらが主として子どものお世話をしてきたか(主たる監護者)」という基準です。
もちろん、当事者の意欲や経済力、家事・育児能力、生活環境、子どもの意思等も考慮されますが、「日常的にお子さんの身の回りのお世話をしてきたのはどちらか」が重視される傾向にあります。
「母親優先」といった、性別を理由とした親権者判断は、(表面的には)減少傾向にある印象ですが、女性が家事・育児を負担している割合が多い日本の家庭状況においては、「主たる監護者」基準によっても、女性が親権者に指定されることが多くなっています。
男性が親権を獲得するためには
このような裁判所の判断基準をふまえると、男性側が親権を獲得するためには、「自分が主たる監護者である」と客観的な事実をもって示すことが非常に重要になります。例えば、日常的な食事の準備、保育園の送迎や連絡帳の記入、学校行事への参加、病気の際の看病などを、主に自身が担ってきたという実績が必要になるでしょう。
【補足】今後の法改正「共同親権」導入の動きについて
最近、離婚後も共同親権にすべきではないかという話が挙がっています。
離婚後の共同親権が導入されれば、上記のような「親権争い」はなくなります。しかし、共同親権になったとしても、離婚後に主に子どもと生活できる(監護者)のは父母のどちらかになります。
そのため、今後共同親権が導入された場合は、上記の「親権争い」が「監護権争い」にスライドしていくことが予想されます。