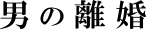法律相談に行くと、「離婚調停」「婚姻費用分担調停」「面会交流調停」など、様々な調停の名前が出てきて戸惑われることがあるかもしれません。相談者様や依頼者様からも、「違いがよく分からない」「どれを利用すればいいのか」といったお声をよく聞きます。
そこで今回は、離婚を考え始めたとき、別居中あるいは離婚後に利用されることの多い、主な調停手続きについて分かりやすく解説します。
離婚や別居に伴いよく利用される調停手続き
離婚に関連して、比較的よく利用される主な調停(または審判)には、以下のものがあります。
- 離婚調停(正式名称: 夫婦関係調整(離婚)調停)
- 離婚そのものに加えて、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割など、離婚に関するあらゆる条件について、話し合いを行います。
- 特徴: 当事者間で離婚に関する全ての条件について合意に至らなければ、調停は「不成立」となり終了します。例えば、「離婚すること自体」には合意ができていても、「面会交流」について合意ができなかった、というような場合でも、離婚調停全体としては「不成立」となります。離婚を実現するためには、別途「離婚訴訟(裁判)」を提起する必要があります。(離婚手続き全体の流れは[こちらの記事へのリンク]をご参照ください。)
- 婚姻費用分担調停
- 離婚が成立するまでの間(主に別居中)の生活費(これを「婚姻費用」と言います。)の分担について話し合います。夫婦には互いに生活を助け合う義務があり、収入の多い方から少ない方へ支払われるのが一般的です。
- 特徴: 話し合いで合意できなければ、自動的に「審判」という手続きに移行し、裁判官が双方の収入等の事情を考慮して支払うべき婚姻費用の額を決定します。
- 面会交流調停
- 別居中や離婚後に、子どもと離れて暮らす親(非監護親)が、子どもと定期的・継続的に会う(面会交流)ための具体的な方法やルールについて話し合います。
- 特徴: 話し合いで合意できなければ、「審判」に移行し、裁判官が子どもの年齢や状況などを考慮して、適切な面会交流の方法や頻度を決定します。
- 子の監護者指定・子の引渡し調停(または審判)
- 別居中に、主にどちらの親が子どもの面倒を見るか(監護者)、子どもをどちらの親元で生活させるかについて話し合います。場合によっては、相手方に子どもを引き渡すよう求めることもあります。
- 特徴: 子どもの監護に関する問題は、緊急性が高い場合や、そもそも話し合いでの解決が難しいケースも少なくありません。そのため、調停をへずに最初から「審判」を申し立てることも多いです。調停で合意できなければ、審判に移行し、裁判官が子どもの福祉を最優先に考えて監護者を決定します。
【ポイント】調停で合意できない場合の進み方の違い
このように、離婚調停は合意できなければ「不成立」で終了し、次のステップ(訴訟)に進むには自らアクションを起こす必要があります。
他方、婚姻費用、面会交流、監護者指定に関する調停は、合意できなくても自動的に「審判」に移行し、裁判所(裁判官)が最終的な判断を下すという違いがあります。
離婚後にも利用できる調停手続き
離婚が成立した後でも、状況の変化に応じて、以下のような調停手続きを利用することができます。
- 財産分与調停(離婚時に財産分与の取り決めをしなかった場合など)
- 養育費(変更)調停(事情の変更による増額・減額請求など)
- 面会交流調停(条件の変更など)
- 親権者変更調停(親権者の変更を求める場合)
- 年金分割の審判または調停
離婚後、元配偶者との間で養育費の支払いが滞った、面会交流がうまくいかない、などの問題が生じた場合も、これらの手続きを利用できます。
おわりに
離婚やそれに伴う問題は、感情的な対立もあり、当事者同士での話し合いが困難なケースが多くあります。調停は、裁判所の関与のもとで冷静に話し合いを進めるための有効な手段です。
どの手続きを利用すべきか、どのように進めればよいかなど、ご不明な点やご不安なことがございましたら、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。個別の状況を詳しくお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。